炎上は起こる前提で備える|広報が知っておきたいSNSリスク管理の基本
2025年11月19日
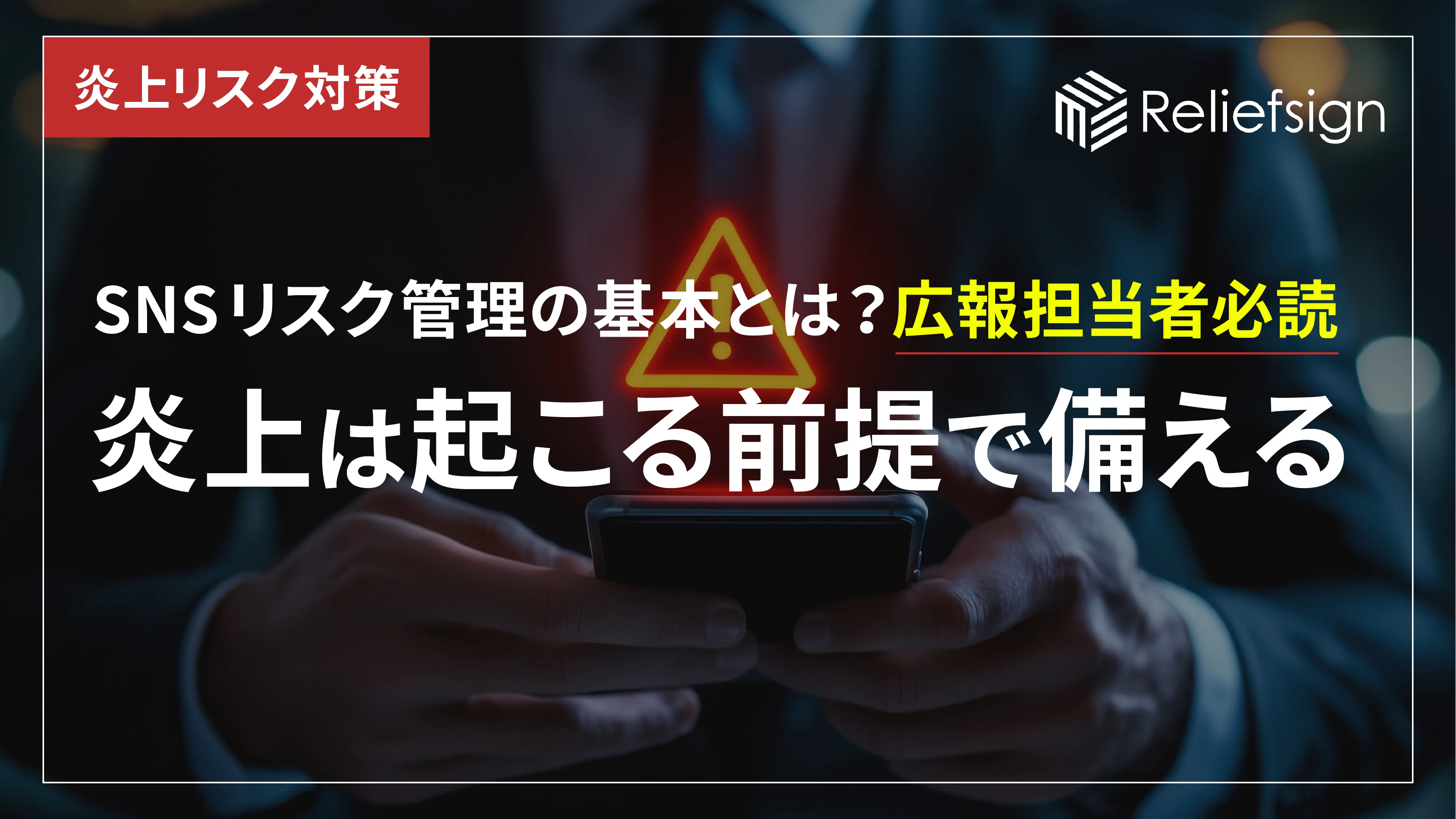
企業がSNSを活用する前に知っておくべき“炎上の現実”
SNSは企業にとって情報発信の場である一方、SNS炎上の火種にもなり得ます。広報や危機管理部門の担当者であれば、「SNSはやらない方がいい」と感じたことがあるかもしれません。実際、炎上が発生すると、企業ブランドの回復には膨大な時間と労力がかかってしまいます。
特に厄介なのは、炎上の原因が自分の部署ではない場合でも、広報が“火消し役”として対応に追われるケースです。
しかも、それはある日突然発生し、通常業務を止めて全力で対応にあたらなければならない状況となっていまいます。メディアが炎上事案を取り上げてしまうと、さらに拡散することもあり、対応の難易度は一層高まります。
そのため企業がSNSを活用する際には、炎上リスクを前提にした運用体制と、広報部門の役割を明確にしておくことが不可欠です。
従業員の個人投稿が企業リスクに直結する時代
最近では、公式SNSアカウントのための投稿ルールや運用ガイドラインなど、炎上対策に取り組む企業が増えてきました。しかし、昨今のSNS炎上事例からわかるように、プライベートのSNS投稿がきっかけで、従業員の所属している企業に「飛び火」するケースも見られます。
たとえ従業員の個人アカウントであっても、投稿内容が企業の価値観やブランドイメージと乖離していると、世間からは「管理責任」が企業に問われる可能性があります。公私関わらず、従業員ひとりひとりが「会社の看板を背負っている」という意識を持たないまま発信した内容が、企業全体の信頼を損なう事態につながるのです。
このようなリスクを防ぐためには、広報・人事・総務部門が連携し、従業員向けのSNS利用ガイドラインや教育体制を整備することが不可欠です。
さらなる炎上を防ぐ広報の準備力
今のSNS時代において、広報担当者は「炎上を起こさない」だけでなく、「起こる前提で備える」ための準備の姿勢が求められます。SNS炎上を未然に防ぐために人事やリスク管理部門と連携し、社内ルールや教育体制を整えることはもちろん、炎上発生後の対応フローを事前に構築しておくことが重要です。
例えば、SNS上の批判投稿の傾向や件数を日常的にモニタリングし、炎上の兆候を早期に察知する仕組みを整えておくこと。
また、炎上時に迅速に発信できる企業コメントやQ&A対応のテンプレートを準備しておくことで、初動対応の質が大きく変わります。
インシデント発生後にしかできない、原因究明や改善策の策定などもありますが、事前にできる準備は多く存在します。企業を守る「無駄になる準備」が、結果的に「無駄になること」こそ、企業にとってはベストなのです。
炎上を防ぐ“投稿しない力”|広報が持つべき判断と感性
SNSでは即時投稿が可能な反面、脊髄反射的な投稿やヒューマンエラー、読み手への配慮不足によって炎上が発生するケースがよくあります。よく言われる「一息おいて読み直す」「夜の投稿は翌朝に見直す」といった工夫は、SNS発信する上で大事な炎上予防の基本です。
とある企業の、SNS運用で成功している担当者からは「公園理論」を意識しているという声もありました。これはSNSを誰もが出入りできる“公共の場”と捉え、自分自身も参加させてもらっていると考えるそうです。実際にも、どう振る舞うべきかを常に考えて判断するため、投稿内容によっては「投稿しない」という決断をすることもあるといいます。
企業としても個人としても、「他人がどう感じるか」という視点を持ち、炎上リスクを避けるために“投稿しない選択肢”を持つことは、SNS時代のリスク管理として非常に有効でしょう。
まとめ
企業にとって、SNSは重要なコミュニティの場である一方、炎上やなりすましといったソーシャルリスクと常に隣り合わせです。そのため、炎上は「いつ起きても対応できる準備」で以下のような、事前対策を行うことが広報の基本姿勢です。
・炎上リスクを前提にした運用体制の構築
・従業員教育とガイドライン整備によるリスク低減
・炎上発生時の初動対応フローとテンプレート準備
・「投稿しない判断」を含む広報の感性強化
これらの取り組みは、企業ブランドを守るだけでなく、SNSアカウントへの信頼性を高める重要な要素です。
さらに詳しく知りたい方は、関連ページをご覧ください。
この記事は、SNSリスクモニタリングサービスなどリスク対策サービスを25年以上支援しているリリーフサインで数多くの企業広報・危機管理対応の経験を持つ企業広報コンサルタントが執筆しています。
ぜひお気軽にご相談ください。






