謝罪会見の失敗を防ぐには?広報が備えるべき準備と炎上対応のポイント
2025年11月10日
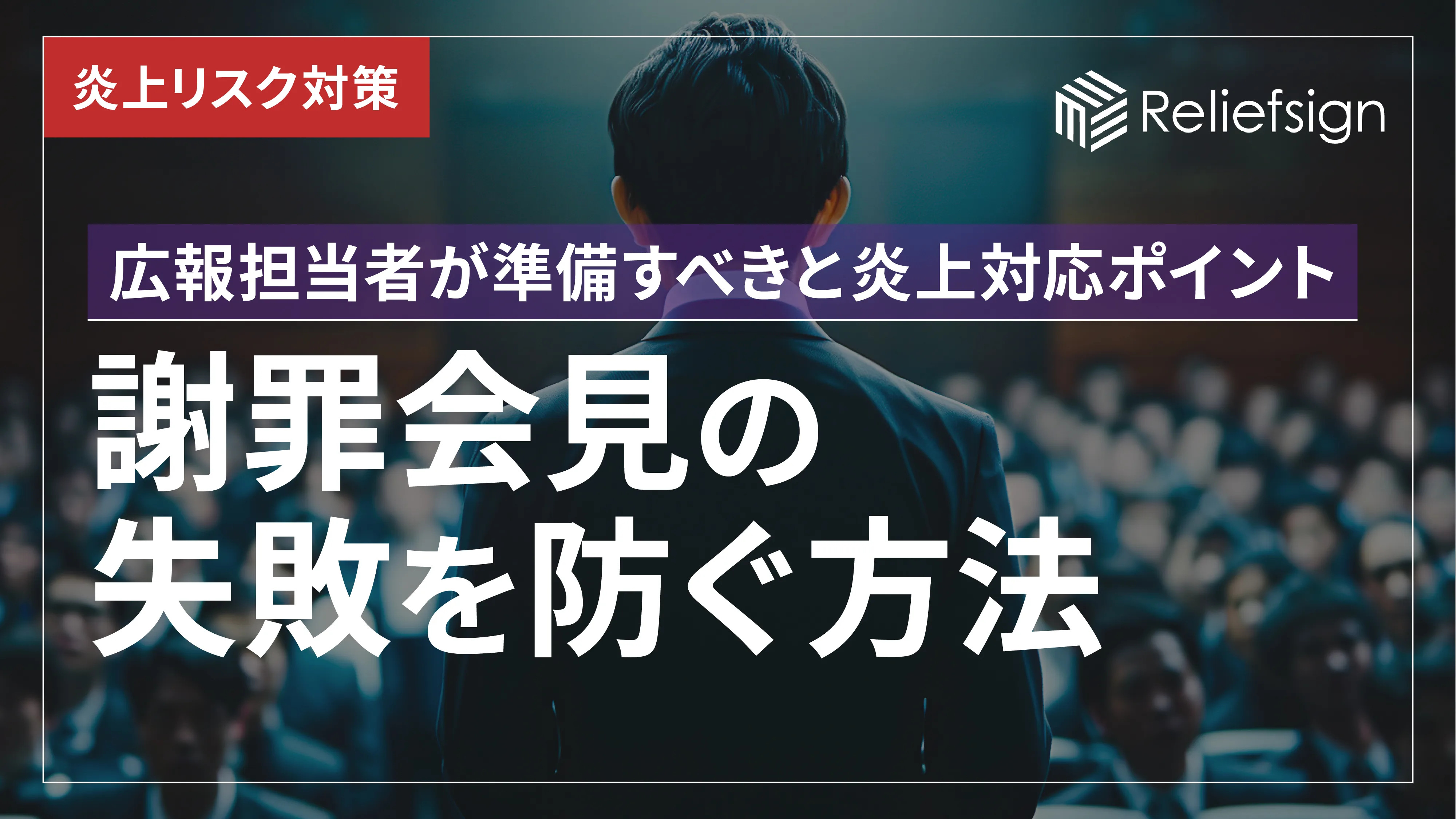
本記事では、厳しい立場に置かれた会見の場で誠意を伝える難しさと、失敗を防ぐために広報が備えるべき準備と対応のポイントを解説します。
謝罪会見は“完全アウェー”|企業広報が直面する現実
謝罪会見は、企業にとって最も緊張感の高い広報対応のひとつです。近年では、会見の様子が冒頭から終了までノーカットで配信されることも多く、発言だけでなく表情や態度、服装の細部に至るまで注目されます。
とある謝罪会見では、登壇者のネクタイの色やおじぎの角度、スーツのボタンの留め方までがSNS上で話題になり火に油を注ぐ形で記事化されたこともあり、まさに“完全なアウェー”の場といえるでしょう。
また、謝罪会見は「企業が問題を起こした後」に行われるため、スタート地点はすでにマイナスの状況。会見中に厳しい質問が飛び交う中で、誠意をもって対応し続けることは、想像以上に困難です。謝罪会見は、企業の信頼を守る“最後の砦”であると同時に、失敗すれば企業のブランド価値をさらに損なってしまうリスクも潜んでいます。
なぜ謝罪会見は失敗しやすいのか?
謝罪会見が失敗しやすいのは、登壇者が極度の緊張状態に置かれるからです。カメラが向けられ、記者に囲まれた中で、厳しい質問に冷静に答え続けるのは、経験豊富な経営者であっても容易ではありません。
謝罪会見での回答内容によっては、発言の矛盾を突かれたり、繰り返し同じ質問をされたりすることで、思考が混乱しやすくなります。さらに、メディア記者は「失言」や「未開示情報」を引き出すために、あえて挑発的な質問を投げかけることもあります。
こうした状況下では、どれだけ準備をしていても、想定外の反応や言葉が出てしまうリスクが高まります。謝罪会見は、そもそも「失敗を招きやすい状況」であるという前提をふまえ、日頃のリスク対策への事前の備えと緊急時での運営体制の強化が不可欠です。
細かな対応の必要性
謝罪会見は、すでに企業への信頼が低下してしまった後に行われる「信頼回復の場」です。
もし、謝罪会見が第2の炎上リスクのきっかけとなってしまえば、さらにブランド毀損が加速してしまいます。だからこそ、謝罪会見を失敗させないための事前準備が不可欠なのです。
以下3つの対応ポイントを軸に、企業広報としての対応を整理しましょう。
●想定Q&Aの作成と回答の言葉選び
●リハーサルによる緊張対策と進行確認
●司会者と回答者の連携体制の構築
想定Q&Aの作成と回答の言葉選び
謝罪会見では、記者からの質問が厳しく、時には意図的に矛盾を突くような内容が投げかけられることもあります。そのため、事前に想定される質問を洗い出し、事実に基づいた、誠実かつ一貫性のある回答を準備しておくことが不可欠です。
特に注意すべきなのは、ブランド信頼回復への意気込みが強すぎるあまり、企業側が曖昧な表現や責任回避と受け取られかねない言葉を使ってしまうケースです。こうした対応は、謝罪の意図が伝わらず、かえって批判を招く原因になってしまいます。
事実に基づいた透明性のある説明と、誠意ある謝罪の姿勢が求められます。謝罪の本質は、被害者や関係者に「謝る気持ち」が伝わることにありますが、それだけでは十分ではありません。謝罪と同時に、再発防止策への具体的な取り組みを示すことが、信頼回復への第一歩となります。
リハーサルによる緊張対策と進行確認
謝罪会見で極度の緊張状態に置かれることは避けられません。だからこそ、事前のリハーサルは、会見を失敗させないために欠かせない準備のひとつです。
リハーサルでは、想定される質問への受け答えだけでなく、謝罪の姿勢が伝わる話し方や表情、服装の確認、そして当日の進行の流れまで、細部にわたる準備が求められます。関係者と会見全体のシミュレーションを行うことで、役割分担やタイミングの調整がスムーズになり、万が一の想定外の事態にも落ち着いて対応できる体制が整います。
会見の本番に向けて、関係者全員で改善点や問題点を確認しておくことで、会見全体の安定感を高めることができるでしょう。
司会者と回答者の連携体制の構築
謝罪会見を円滑に進めるためには、回答者だけでなく、司会者との連携体制が極めて重要です。司会者は単なる進行役ではなく、会見全体の空気を調整し、緊張を和らげる“調整役”としての役割を担います。
特に広報担当者が司会を務める場合、経営層との信頼関係やメディア対応の経験があることが望ましく、質問の切り替えや間の取り方、時間配分などを柔軟にコントロールする力が求められます。リハーサルの段階から司会者がリードし、会見の流れをシミュレーションしておくことで、関係者間の連携がスムーズになり、想定外の事態にも落ち着いて対応できる体制が整います。
謝罪会見では、緊張や感情の高まりから発言がエスカレートする場面もありますが、司会者が冷静に場をコントロールすることで、企業としての誠実な姿勢を保つことができます。会見の成功は、回答者だけでなく、司会者のスキルと連携力にも大きく左右されるのです。
回復しづらい戻らない企業ブランド
しかし、謝罪会見を行ったからといって、企業ブランドがすぐに回復するわけではありません。むしろ、会見の対応次第では、ブランド毀損がさらに加速するリスクもあります。謝罪会見の本質は、被害を受けた方々に対して誠意をもって謝罪の意思を伝えることです。
私たちが謝罪会見の実施前に企業に伝えているのは、「どんな理由があっても、被害や迷惑をかけた事実がある以上、まずはその方々に謝罪の気持ちを届けることが最優先」という姿勢です。メディアを通じて謝罪する場面では、カメラの向こうにいる被害者に語りかけるような気持ちで臨むことが大切です。
もし、謝罪会見の“成功”があるとするならば、被害者に謝罪の気持ちが届くことが最も重要なことになるでしょう。
企業への信頼は「謝ったから戻る」のではなく、「誠意ある謝罪の意思が被害者に伝わり、再発防止策を着実に実行していくこと」のプロセスを経て、少しずつブランドの信頼を取り戻していくものです。その手順を飛ばしてのブランド回復は厳しいでしょう。
まとめ
謝罪会見は、企業が信頼を取り戻すための大事なきっかけの場です。誠意ある謝罪の姿勢と、再発防止策への真摯な取り組みがなければ、ブランドは回復しません。謝罪会見を行う根本の目的は、会見の場を支えるだけでなく、企業の姿勢を社会に伝えることです。事前の準備と社内連携を徹底することで、謝罪会見は単なる“お詫びの場”ではなく、信頼を再構築するための戦略的な広報活動へと変わります。
この記事で紹介したポイントを参考に、謝罪会見への事前準備の重要性を理解しましょう。
さらに詳しく知りたい方は、関連ページをご覧ください。
この記事は、SNSリスクモニタリングサービスなどリスク対策サービスを25年以上支援しているリリーフサインで数多くの企業広報・危機管理対応の経験を持つ企業広報コンサルタントが執筆しています。
ぜひお気軽にご相談ください。






